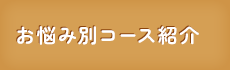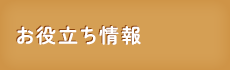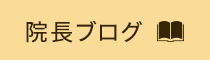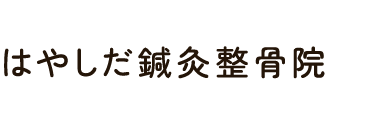夜間のズキズキする痛み、上に手が上がらない、服の脱ぎ着がつらい…。いわゆる「五十肩(凍結肩・肩関節周囲炎)」は、時期ごとに適したケアが異なります。本記事では段階別のセルフケアと、受診の目安を分かりやすくまとめました。
夜間のズキズキする痛み、上に手が上がらない、服の脱ぎ着がつらい…。いわゆる「五十肩(凍結肩・肩関節周囲炎)」は、時期ごとに適したケアが異なります。本記事では段階別のセルフケアと、受診の目安を分かりやすくまとめました。
五十肩とは?段階と回復の全体像
五十肩(凍結肩・肩関節周囲炎)は、明らかな外傷がないのに肩の痛みと可動域制限が出る状態です。多くは次の3段階をたどります。
- 疼痛期(約1〜3カ月):夜間痛・じっとしていてもズキズキ。動かすと鋭い痛み。
- 拘縮期(約3〜9カ月):痛みは落ち着くが固さが前面に。可動域が狭くなりがち。
- 回復期(約6〜18カ月):少しずつ動きが戻る。適切な運動で回復が加速。
個人差が大きく、糖尿病・甲状腺疾患・長期の不動などがあると経過が長引くことがあります。
危険サイン(今すぐ受診)
以下に当てはまる場合は整形外科などの受診を優先してください。
- 転倒・外傷直後からの強い痛みや急な脱力(腱板断裂の疑い)
- 安静時・夜間の強い痛みが急に悪化、発熱や全身倦怠を伴う
- 手に広がるしびれ・力が入らない(頚椎疾患・神経症状)
- がんの既往/治療中、長期ステロイド内服、糖尿病で痛みが急増
- 赤み・熱感・腫れが強い(感染や石灰沈着性腱炎などの可能性)
痛みが強い時期(疼痛期)のセルフケア
目標:痛みを鎮め、肩を「守りながら」小さく動かす。痛みスケール0〜10で3を超えない範囲。
1) 楽な姿勢・寝方
- 横向き:痛い側を上にして、脇に小枕。抱き枕で肩を少し前に。
- 仰向け:肘の下にタオル、前腕を胸の上に置く。肩が後ろに引かれないよう調整。
2) 温め・冷やし
- 温め:ホットパックや入浴で血流を促す(10〜15分、高温/長湯は避ける)。
- 冷却:夜間痛が強い場合に10分程度。増悪する方は中止。
3) 超やさしい運動(1〜3回/日)
- 肩甲骨のセット:背筋を軽く伸ばし、肩をすくめず胸を開く×5回。
- ペンデュラム(振り子):前屈みで腕を脱力し、直径10〜20cmで前後・左右・円運動 各10周。
- テーブル滑り(前方):テーブルに手を置き、痛くない範囲で前に滑らせる×10回。
ポイント:鋭い痛みが出たら即中止。就寝前のホットシャワー+振り子運動が夜間痛の軽減に有効です。
固まってくる時期(拘縮期)のセルフケア
目標:無理のないストレッチで関節包の柔軟性を回復。痛み0〜10で3以内、反動をつけない。
1) ウォームアップ
- 5〜10分の温熱+肩甲骨の小さな動き(すくめない・すりこぎ運動)。
2) 基本ストレッチ(1〜2回/日)
- 壁這い(屈曲):指で壁を歩かせて腕を上げる。20〜30秒×3セット。
- 外旋ストレッチ:脇にタオルを挟み、棒や傘で痛い側の前腕を体の外側へ。20秒×3。
- クロスボディ・ストレッチ(水平内転):反対手で肘を抱え、胸の前で軽く引き寄せる。20秒×3。
- タオル背中回し:背中でタオルの上下引き。痛くない側主導で可動域を補助。20秒×3。
コツ:息を止めない。翌日の張りは許容、鋭い痛みや夜間痛の増悪は強度オーバーです。
動く時期(回復期)のセルフケア・筋トレ
目標:可動域の維持拡大+ローテーターカフ・肩甲帯の協調性を取り戻す。
1) 可動域ドリル(毎日)
- テーブル/壁スライド(上・横・前斜め)各10回×1〜2セット。
- 胸椎伸展(椅子にもたれて両手頭の後ろ、背中を反らす)10回。
2) 筋力・協調トレ(週3〜4回)
- 等尺性外旋・内旋:肘を脇に固定し、壁やドア枠を5秒押す×5回。
- セラバンド外旋/内旋:軽負荷で15回×2。痛み3以内。
- 前鋸筋パンチ(仰向けで拳を天井へ突き上げ、肩甲骨を前に滑らせる)15回×2。
- 横向き外旋(軽ダンベル0.5〜1kg)15回×2。
負荷は「翌日の痛み・可動域悪化がない」範囲で段階的に。頭上や後ろ手の動作も、日常動作に合わせて徐々に再開します。
悪化させやすいNG行動
- 鋭い痛みを我慢して可動域を無理にこじ開ける
- 痛みが強い時期に強圧マッサージや強いストレッチ
- 長期間ほぼ動かさない(不動)ことで拘縮を助長
- 重い物を腕を伸ばして持つ、急な頭上動作
- 常に痛い側を下にして寝る習慣
日常生活のコツ(寝方・服の脱ぎ着・デスク)
- 服の脱ぎ着:前開きの服を活用。上着は「痛くない側→痛い側」の順に袖を通す、脱ぐ時は逆。
- 家事:高い棚の物は踏み台で高さを合わせる。鍋や洗剤は体に近づけて持つ。
- デスク:肘は70〜90度で支持、肩をすくめない。マウスは体から離しすぎない。
- 睡眠:抱き枕+脇枕でリラックス位。夜間痛には就寝前に温めと振り子運動。
- 通勤・運動:痛みが落ち着けばウォーキングや下半身運動で循環を維持。
受診の目安と医療で検討できること
- 夜間痛が2〜3週間以上おさまらない、可動域が急に悪化
- 力が入らない・バンザイでガクッと抜ける感じが続く
- 糖尿病・甲状腺疾患があり経過が長引く、自己管理が不安
- 画像検査や注射治療(関節内ステロイド、ハイドロダイレーション等)を検討したい
まずは状態評価とセルフケア設計を行い、必要時は整形外科での検査・注射療法を併用するのが有効です。
当院のサポート(鍼灸+手技・運動指導)
- 評価:問診・徒手検査で疼痛期/拘縮期/回復期を判定。頚椎や胸椎、肩甲帯の連動も確認。
- 施術:疼痛期は炎症に配慮したやさしい手技・鍼灸で鎮痛と筋緊張の緩和。拘縮期〜回復期は関節モビライゼーション(段階に応じてグレードI〜IV)、軟部組織リリース。
- 運動処方:段階別の可動域ドリルとローテーターカフ/肩甲骨トレをホームプログラム化。
- 生活アドバイス:寝方・デスク調整・家事の工夫など、痛みを増やさないコツを具体的にお伝えします。
- 通院目安:週1〜2回から開始し、経過に応じて間隔を調整。医療機関での検査・注射が必要と判断した場合は受診を推奨します。
まとめ(大切なポイント)
- 時期に合わせて「守る→伸ばす→鍛える」を切り替える
- 痛みは0〜10で3以内を目安。夜間痛の悪化は強度オーバーのサイン
- 数週間で変化が乏しい、力が入らない時は早めに専門家へ
関連ページ
よくある質問(FAQ)
Q. どのくらいで良くなりますか?
A. 個人差がありますが、数カ月〜1年ほどで自然回復傾向です。適切な運動と生活調整で回復を早められます。
Q. 画像検査(レントゲン・MRI・エコー)は必要ですか?
A. 典型的な五十肩は画像なしで対応可能なことが多いですが、急な筋力低下や外傷歴、経過が長引く場合は医療機関での検査をおすすめします。
Q. 温めと冷やし、どちらが良い?
A. 疼痛期の夜間痛には短時間の温めが合うことが多いです。冷却で楽になる方もいるため「楽な方」を10〜15分の短時間で行いましょう。
Q. 運動はどのくらいの痛みまでやって良い?
A. 目安は痛み3/10以内、反動をつけないこと。鋭い痛みや翌日の可動域悪化があれば強度を下げます。
Q. 注射(ステロイド)や水注入(ハイドロダイレーション)は受けた方がいい?
A. 疼痛期の強い痛みには有効な場合があります。担当医と相談のうえ、運動療法と併用すると効果的です。
ご予約・アクセス
院名:はやしだ鍼灸整骨院
住所:大阪市東住吉区桑津1-12-27
電話:06-6713-7755
診療時間:平日 9:00-13:00 / 16:00-20:00、土曜 9:00-13:00 休診:日曜・祝日
- HP:https://hayashida-sinkyuu-seikotsu.com
- 公式LINE(整体):https://x.gd/l1N2x
- 地図(Googleマップ):こちらを開く
初診時は肩周りが動かしやすい服装でご来院ください。お困りの方はお電話またはLINEからお気軽にご相談ください。
監修・参考情報
監修:柔道整復師(はやしだ鍼灸整骨院)
- JOSPT Clinical Practice Guideline: Adhesive Capsulitis (2013; updates)
- BESS/BOA Patient Care Pathways: Frozen Shoulder (2016)
- AAOS OrthoInfo: Frozen Shoulder (Adhesive Capsulitis)
- BMJ Best Practice: Frozen shoulder (最新更新)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。症状・経過には個人差があるため、自己判断で無理をせず専門家にご相談ください。